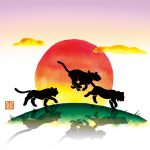はじめに

近年、システム開発や業務改善などのプロジェクトは、人材不足や工程の複雑化などさまざまな要因により、マネジメントの難易度が高まっています。
「プロジェクトが思ったように進まない」「途中で手戻りが多発してしまう」といった声をよく耳にします。
特に「品質管理」や「リソース不足」に関しては、弊社にも多くのご相談が寄せられています。
これらの課題は、プロジェクト全体の進捗や成果物の品質、さらにはチーム全体の生産性にも大きく影響します。
本稿では、プロジェクトマネジメントの現場で実際に多く見られる3つの課題と、それぞれに対する改善の方向性をご紹介します。
プロジェクト遂行に課題やお悩みを感じている方にとって、少しでも解決のヒントとなれば幸いです。
プロジェクトにおける役割の簡単整理

本題に入る前に、プロジェクトにおける主要な役割を整理しておきましょう。
PM(プロジェクトマネージャー)は、プロジェクトの目標達成に向けて進捗・品質・コスト・リスクを統括し、最終的な成果に責任を持つ立場です。
一方、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)は、PMのサポート役であり、PMが意思決定に専念できるよう情報収集・分析、各種調整を行うことでプロジェクト管理を支援し、全体の運営を統制します。
PMが「現場の指揮」を担うとすれば、PMOは「プロジェクト運営全体を整える役割」と言えるでしょう。両者が連携することで、安定したプロジェクト推進が可能になります。
ただ、プロジェクト成功のためには、この二者だけではなくメンバー全員の協力が欠かせません。
プロジェクトマネジメントでの3つの課題

それではプロジェクトを進めるにあたってどのような課題があるのか、ご紹介していきます。
コミュニケーション不足
プロジェクトを進めるにあたって最も重要といえる「コミュニケーション」ですが、コミュニケーション不足が課題となっている企業やプロジェクトも少なくありません。
- メンバー間・ベンダー間の情報共有
現場での不十分な情報共有が原因で認識のずれやタスクの重複、対応漏れなどが発生するケースがあります。
たとえば、「誰がどの課題を対応しているのか分からない」「別ベンダーが同じ不具合を個別に対応していた」など小さな齟齬が積み重なり、結果的に品質や納期に影響を与えることがあります。
このような問題の背景にはコミュニケーションのルールや手段が明確化されていないことが挙げられます。
そのため、プロジェクト計画書には「コミュニケーション管理計画」を設定し、チャットツール・メール・Web会議などの手段やそれぞれの目的、使用ルールを定めておくことで、情報の混乱を防ぐことができます。
しかし、ツールを使っての情報共有のみではメッセージの解釈が異なったり、依頼内容や優先度の認識がずれたまま作業が進むケースもあります。
そのため、PMは週次会議などの定例ミーティングを設け、ベンダー間の認識合わせや、課題の棚卸しを行う場を設定することが求められます。
コミュニケーションの場を設けることも、プロジェクトマネジメントの一部として捉えることが重要です。 - 顧客との意思疎通の難しさ
プロジェクトは「顧客のニーズに合ったものをつくる」ことが前提であるため、顧客からどれだけ的確にヒアリングできているかが、最終的な顧客満足度を大きく左右します。
近年は、顧客との打ち合わせをWEB会議のみで行うケースも増えていますが、オンラインでのやり取りだけでは本質的なニーズや課題の背景を引き出せないことがあります。実際に現場を訪問し、業務目的や背景を直接確認することで、要件定義の精度が大きく向上します。
ここで十分なヒアリングができていないと「顧客の期待と異なるシステムが構築されてしまう」「再設計が必要になる」といった大きな手戻りにつながります。
こうしたリスクを事前に想定し、顧客とのコミュニケーションを能動的に設計・実践していく姿勢が求められます。
品質管理
次に、品質管理に関しての課題です。
特に上流工程(要件定義・設計)で品質を作り込む意識が欠けると、後工程での手戻りが増大し、結果的にコストと工期に影響します。
ベンダー主導で要件定義を行う場合、「どんな機能を作るか」という技術的視点に偏りがちです。しかし顧客が求めているのは「この業務を改善したい」「こんな成果が得たい」という業務視点です。
このズレを埋めるためには「業務目的 → 必要な要件 → 実現する機能」の流れを明確化することが重要です。
要件の抜け漏れを防ぐためにトレーサビリティ表を活用することで、要件とテスト項目をチェックしながら品質を可視化することができます。

また、品質は個人のスキルや努力に頼るものではなく、組織としての仕組みで担保すべきものです。
特定の担当者の経験や判断に依存した状態では、属人化によって品質のばらつきが生じやすく、再現性のある成果を得ることは困難です。
そのためISOなどの国際標準にもあるように、品質は要件定義・設計・テストといった全工程を通じて体系的に管理することが求められます。
各フェーズで「何を」「どの基準で」「誰が」確認するかを明確にし、チェックポイントを仕組みとしてプロジェクトに組み込むことが重要です。
リソース不足
最後に挙げるのはPM人材のリソース不足です。
近年、DX推進の加速により、求められる役割はますます高度化・複雑化しています。
その一方で、経験豊富な人材は慢性的に不足しており、1人のPMが複数のプロジェクトを同時に抱えるケースも少なくありません。
結果として、進捗確認や品質チェックといった細部までの管理が手薄になり、問題の早期発見ができないまま、リリース直前に大きな手戻りが発生してしまうこともあります。
経験の浅いPMが単独でプロジェクトを任されることも多く、リスク管理・課題把握・ベンダーコントロールといったマネジメント領域が十分に機能しないリスクもあります。
さらにPM自身が複数タスクを兼務しているケースでは、本来注力すべきマネジメント業務が後回しになってしまい、チーム全体のパフォーマンス低下を招くこともあります。
またPMだけでなくPMOの人材も不足しています。
特に複数案件を横断的に管理するPMO機能は、PMを支える重要な役割ですが、経験や知見を持つ人材が限られており、十分に機能しないケースも見られます。
プロジェクトの安定運営には、PM・PMO双方を含めた体制整備が欠かせません。
改善策

ご紹介してきた3つの課題は個人の努力のみでの解決は難しく、組織としての仕組み化が解決のカギとなります。ここからは「現場でできること」と「QualityCubeの支援」の両面からの改善策を提示します。
現場で意識できるポイント
情報共有は相手に“届かせる”
情報をチャットで送ること自体は簡単です。
しかし、相手に正しく伝わっていなければ、それは「共有できている」とは言えません。重要なのは情報が正しく理解されることです。
定例会議などでの認識合わせや決定事項の明文化を徹底するだけでも、手戻りは大幅に減らすことができます。
品質は“上流でつくる”“仕組みで守る”
品質はテスト段階ではなく、上流工程で設計し仕組みとして維持するものです。
顧客のニーズを聞き切ることはもちろん、要件の目的明記やレビュー観点の標準化など、日々のプロセスに仕組みを組み込むことが重要です。
PMを“孤立させない”チーム体制
PMがリソース不足に陥っているプロジェクトでは、「管理が追いつかない」「報告が後手に回る」といったリスクが顕在化します。
この状況を防ぐには、PMをチーム全体で支援することが解決策となります。
メンバーが主体的に進捗や情報を共有し、PMを支える意識を持つことで、プロジェクト全体の安定と成果の最大化につながります。
QualityCubeの支援
現場で工夫できることは多くありますが、すぐに状況を変えることは難しいかと思います。QualityCubeで行っている支援を一部ご紹介いたします。
プロジェクトマネジメント支援
プロジェクトマネジメント支援の一環でPM代行支援を行っております。 PMとしてプロジェクトへ参画し、進捗や課題の可視化、品質管理を通じてプロジェクト成功へ導きます。
マネジメント手法の標準化や課題の見える化を推進し、クライアント企業が自走できるプロジェクト体制の構築を支援します。
プロジェクト実務支援
上流から下流までのあらゆる工程を支援しています。
特に、要求定義・要件定義はプロジェクトの成功に大きな影響を与えるにもかかわらず、難易度が高く苦手意識を持たれている方も少なくありません。
QualityCubeでは現場に寄り添い、要件整理や課題解決を通じて円滑にプロジェクトを進められるよう支援します。
品質コンサルティングサービス
ISOなどの国際基準に基づいた品質マネジメント体制の構築を支援しています。
単に不具合を防ぐためのチェックではなく、「上流から品質をつくり込む仕組み」を整えることを重視しています。
具体的には、レビュー基準やドキュメント整備ルールの策定、品質基準の可視化、などを通じ、属人的な判断に頼らない品質管理を実現します。
これにより、組織として継続的に高品質な成果を生み出せる“再現性のある品質マネジメント”を構築することを目指しています。
これらのサービスにより、QualityCubeは単なる支援者ではなく、企業とともに仕組みを整え、現場が自走できる体制づくりをサポートします。プロジェクトの安定推進と持続的な成長を支える伴走者として、組織のマネジメント力向上に貢献します。
まとめ

本稿ではプロジェクト推進における主要な課題として、コミュニケーション・品質管理・リソースの3つの観点を取り上げました。
いずれも個人の努力に依存せず、組織全体として仕組み化し運用することで、安定した成果につながります。
QualityCubeは、企業やプロジェクトに合わせた最適な仕組みを構築し、現場が自走できる体制を育てることで、プロジェクトの成功と持続的成長を支援します。


-150x150.jpg)



-300x141.jpg)